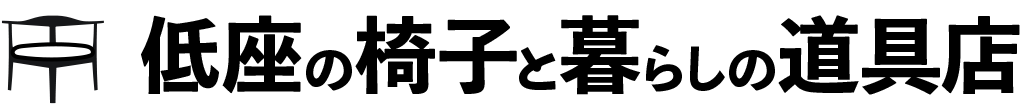大西暢夫監督 長編ドキュメンタリー映画『炎はつなぐ』
和ろうそく作りに関わるさまざまな職人たちの仕事と、それを支える伝統の技が、謎解きのようにつながっていく様を描いたドキュメンタリーをスタッフが紹介。

和ろうそく作りから紐解く、工芸材料の有機的ネットワーク
はじめまして。低座の椅子と暮らしの道具店のスタッフ井上です。私は2024年1月に実店舗の「モノ・モノ」に入社し、主に金継ぎサービスの担当をしています。以前は生活雑貨店で販売の仕事をしていましたが、40代になってから一念発起。岩手で漆塗りを学んできました。
その時に教わった先生の師匠に当たるのが町田俊一先生(モノ・モノの金継ぎ教室講師)です。地元の神奈川に戻ってから、町田先生のアシスタントをしたいと思い、金継ぎに関わる業務をお手伝いするようになりました。
モノ・モノでは浄法寺と越前の漆器を販売しています。つくり手の一人、越前漆器の山本隆博さんが東京まで出張して観たい映画があるということで知ったのが、ドキュメンタリー映画『炎はつなぐ』でした。
チラシのキャッチコピー「ゆらぐ和ろうそくの炎は、消えて土に還り、そしてまた灯る―」を読んで、和ろうそくづくりの映画かと思って観ていました。しかし、なかなかろうそくが出てきません。蚕を育てる人、藍染をする人、和紙の原料をつくる人、ハゼの実を穫る人、漆を掻く人…。
しかし観ているうちに、だんだんその訳に気づきました。監督が興味をもって、知りたいと話を聞きに行く。その話からまた知りたいことが生まれて、話を聞きに行く。そうやって映画がつながっていくように、ものづくりは全てがつながっているのだ、と。そのたくさんのつながりの中で、和ろうそくはできあがっていく。そのつながりは一方向ではなく、支えられている人は、別の誰かを支えていて、また他の誰かからも支えられている。大きな循環がテーマの映画だったのです。
つながっているからこそ、どこか一つが途絶えてしまえば、その影響は一つにとどまらず、他にも仕事を続けられなくなる人が出てきてしまいます。映画に登場する方の多くがご高齢なので、これがいつまで続くだろうか、続いてほしい、そんな気持ちでいっぱいになります。でも、映画には跡を継いでいる方も登場します。私と同じ40〜50代の方も多く、中には20代の若者もいます。私が漆塗を学んだ研修所にも毎年研修生が入ってきます。2025年の今に続いている事実が、すでに希望なのかもしれません。
厳しい競争社会、物価の上昇、気候変動、コロナ禍を経験し、少しずつですが世の中の人の価値観が変化してきています。この映画に登場する人のように生きるのは難しいですが、その仕事に価値を見出すことで、見える世界が変わり、ふつうの人の仕事が世界を支えていることを思い出すことができます。さらに、自分の仕事も誰かを支えていると感じられたら、少し元気が湧いてくるのではないでしょうか。
映画を通して、登場する人たちが自分たちの仕事について楽しそうに話している姿が印象的でした。それは監督が驚いたり感心したりしながら聞く姿勢によって、つながりが生まれたからでしょう。興味をもって話を聞くことだけでも、大きな力になり得るのです。もともと私が生活雑貨店で働き始めたのは、昔から脈々と続いている手仕事に興味があったことと、それがこれからも続いていくために、自分は「伝える」仕事をしたいという思いからでした。この映画を観て、はじまりの気持ちを思い出すことができました。
大西暢夫監督・長編ドキュメンタリー映画『炎はつなぐ』は、全国のミニシアターで順次公開予定とのこと。ものづくりに興味のある方はもちろん、仕事、家族、ひいては生き方について考えたい方(=すべての方)に観てほしい映画です。
(スタッフ・井上)
著者の紹介

低座の椅子と暮らしの道具店編集部は、東京・中野のクラフトショップ「モノ・モノ」内にあります。現在のスタッフは7名(在宅勤務含む)。漆塗研修所の修了生、木工インストラクター、ウェブデザイナー、元フリーライター、通販会社や家具メーカーの元社員など、多彩な顔ぶれがそろっています。